ニットは糸になる以前の状態や製品になった状態など、いろいろな段階での染め方ができます。
|
トップ染め |
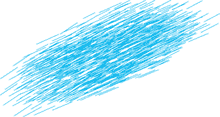 |
紡績前のカーディングされて繊維が平行になった綿(スライバー)の状態のときに染めます。もしくは、綿段階で染まった何色かをミックスして霜降り状にすることができます。一般に紡毛糸はトップ染が基本です。風合がよく、堅牢度もよいです。(縮絨後) |
|
綛染め |
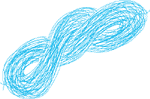 |
250g、500g、750gの単位。シルク糸に多く使われます。チーズ染より風合がよいです。 |
|
生地染め |
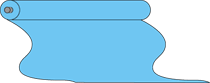 |
丸編機や経編機、流し編みにした物を染めます。 |
|
チーズ染め |
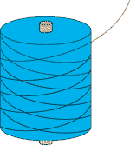 |
撚糸された糸を一定の角度の綾目で円筒状に巻いたものをチーズといい、この状態で染めます。糸染めとも言います。 |
|
ピースダイ |
 |
製品になった状態で染める。一般的に紡毛糸を使ったフルファッションの製品を染めます。色によって寸法の差を弱冠出ますが、新しい色の追加や売れる色の早期補充がきる点などのメリットがあります。風合もよいです。 |
染める前の糸は生地糸といいますが、染め上がると風合が変わるので生地糸の段階で風合を判断することはできません。
厳密にいえば、染め上がった色によっても風合は異なります。
特に、同じ糸をトップのものと糸染めしたもの両方で製品にすると、トップのものの方が風合はよいです。
希望する色を試験的に使用する素材に染めてみることです。
ビ−カ−依頼色は、使用する素材と同じか、近い原料の糸や生地に色が付いたもので指示するのが理想的で、且つ、染めたときのずれが少なく上がります。
指示された色はCCM(カラーコンピュータマッチング)という機械で色の構成を分析します。(紙でも、印刷物でも分析できます)
|
トップ染め |
CCMで分析した色の綿を電子計りでそれぞれ計り、毛をブレンドします。むらのないように平均的にブラシでカ−ペット状にまとめて、「手引き」という機械で糸にします。 |
|
糸染め |
フラスコにCCMで分析した染料を入れ、生地もしくは糸を入れます。 |
ビーカーで色を決定してから、展示会サンプル用、製品用の糸を染めますが、時間の無い場合は平行ビ−カーという手段を取ります。
この場合はビーカーと同時に展示会サンプル用、製品用の糸を染めます。