崌惉慇堐偼偦傟偧傟尨椏暘巕偼堘偆傕偺偺丄偡傋偰崌惉崅暘巕乮崌惉億儕儅乕乯偐傜偱偒偰偄傑偡丅
娙扨側暘巕乮儌僲儅乕乯偑屳偄偵庤傪偮側偄偱丄悢昐偐傜壗枩偲偮側偑傞偲丄巒傔偺暘巕偱偼偲偰傕峫偊傜傟側偄惈幙偺暔幙乮億儕儅乕乯偵側傝傑偡丅偙偺傛偆偵丄暘巕乮儌僲儅乕乯傪偮側偓崌傢偣傞偙偲傪廳崌偲偄偄丄暘巕偺偮側偑偭偨悢傪廳崌搙偲偄偄傑偡丅
慇堐偵偱偒傞偺偼尷傜傟偨億儕儅乕偱偡丅嵶挿偔堷偭挘偭偰怢傃傞偙偲傗丄偱偒偨嵶偄巺偑廮傜偐偔丄嫮偔丄慇堐偲偟偰偺惈擻傪帩偭偰偄側偗傟偽側傝傑偣傫丅僫僀儘儞丄億儕僄僗僥儖丄傾僋儕儖丄價僯儘儞丄億儕僂儗僞儞側偳偱偡丅
億儕僄僗僥儖
偄偭偨傫億儕僄僗僥儖億儕儅乕傪嶌偭偰偐傜丄擬偱梈偐偟偰朼巺岥嬥偺彫偝側岴偐傜墴偟弌偟堷偭挘偭偰巺偵偟傑偡丅乮梟梈朼巺乯
慇堐偵揔搙側挘傝丄崢偑偁傝丄抁慇堐偼柸傗梤栄偵偵偰偄傑偡丅傑偨丄挿慇堐偼對偺晽崌偵嬤偔丄慇堐偺懢偝傗抐柺宍忬傪曄偊偨傝丄屻偺尭検壛岺偱晽崌傪帺桼偵挷愡偱偒傑偡丅
揔摉側嫮偝丄怢傃丄偟側傗偐偝偑偁傝丄偟傢偵側傝偵偔偔丄岝傝乮巼奜慄乯偵偝傜偝傟偰傕庛偔側傝傑偣傫丅擬偵嫮偔丄挿慇堐偺悡崅壛岺偑梕堈偱偡丅擬僙僢僩惈偑傛偄偲偄偆摿挿偑偁傝傑偡丅梟梈朼巺偱娵抐柺埲奜偵丄堎宆抐柺丄嬌嵶慇堐丄暋崌慇堐側偳丄摿庩側宍懺偺慇堐傪斾妑揑偮偔傝傗偡偄慇堐偱偡丅傑偨丄斀暔偵偟偰壵惈僜乕僟偱慇堐偺昞柺傪彮偟梟偐偡乮尭検壛岺乯偲慇堐偑嵶偔側傝晽崌偑廮傜偐偔側傝傑偡丅偨偩丄100亷埲忋偱愼傔側偗傟偽側傜側偄偲偄偆摿庩惈傕偁傝傑偡丅旕忢偵僐僗僩偑埨偔丄1哃偁偨傝亸100埲壓偱偡丅
 |
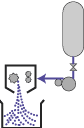 |
|||||
|
僄僠儗儞 |
僄僠儗儞僌儕僐乕儖 |
|||||
|
愇桘 |
僷儔僉僔儗儞 |
巁壔 |
僥儗僼僞儖巁 |
廳崌 |
億儕僄僗僥儖億儕儅乕 |
|
|
億儕僄僗僥儖億儕儅乕傪偮偔偭偰偐傜梟梈朼巺 |
||||||
|
|
||||||
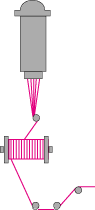 |
丂丂丂 | 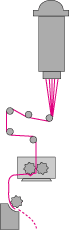 |
||||
| 丂 | ||||||
|
梟梈朼巺 |
億儕僄僗僥儖 |
梟梈朼巺 |
億儕僄僗僥儖 |
|||
| 丂 | ||||||
|
億儕僄僗僥儖僼傿儔儊儞僩偺惢憿岺掱 |
億儕僄僗僥儖僗僥乕僾儖偺惢憿岺掱 |
|||||
|
|
||||||
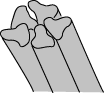 |
丂 | 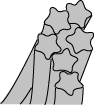 |
丂 |  |
|
嶰梩抐柺 |
屲梩抐柺 |
拞嬻 |
||
| 丂 | ||||
|
億儕僄僗僥儖偺抐柺 |
||||
僫僀儘儞
僫僀儘儞偺億儕儅乕偵偼僫僀儘儞6偲僫僀儘儞66偑偁傝丄偦傟偧傟尦偺尨椏偑堘偄傑偡丅
梟梈朼巺偱丄挿慇堐偑庡懱偱偡丅慇堐偺摿挿偲偟偰偼嫮偔丄摿偵杸嶤偵嫮偄摿挜偑偁傝傑偡丅怢傃偑偁傝丄廮傜偐偄丅愼怓偟傗偡偔丄怓偑旤偟偔弌傑偡丅斀墳惈偵晉傫偱偄傞偺偱丄栻昳偵傛傞屻壛岺偑偟傗偡偄偲偄偆惈幙傕偁傝傑偡丅擬僙僢僩偑偱偒偰丄悡崅壛岺偵揔偟偰偄傑偡丅尨椏僐僗僩偑傗傗崅偄偺偑擄揰偱偡丅挿婜娫偍偔偲墿曄偟傑偡丅
朼栄巺傪嶌傞帪偵丄栄偵15%傎偳偺僫僀儘儞傪崿偤偰朼愌偡傞偙偲偑傛偔偍偙側傢傟傑偡偑丄偙傟偼僫僀儘儞偑廮傜偐偔丄忎晇偱栄偲摨偠愼椏偱愼傔傞偙偲偑偱偒傞偨傔偱偡丅
 |
||||||
|
愇桘 |
僔僋儘僿僉僒儞 |
兠僇僾儘儔僋僞儉 |
廳崌 |
僫僀儘儞6億儕儅乕 |
||
| 丂 | ||||||
|
僫僀儘儞6偺惢憿岺掱 |
||||||
|
|
||||||
 |
||||
|
愇桘 |
傾僕價儞巁 |
廳崌 |
||
|
僿僉僒儊僠儗儞僕傾儈儞 |
僫僀儘儞66億儕儅乕 |
|||
| 丂 | ||||
|
僫僀儘儞66偺惢憿岺掱 |
||||
| 丂 | ||||
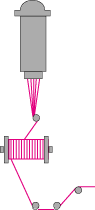 |
丂丂丂丂 | 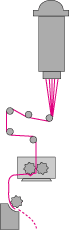 |
||||
|
梟梈朼巺 |
僼傿儔儊儞僩 |
梟梈朼巺 |
僫僀儘儞 |
|||
| 丂 | ||||||
|
僫僀儘儞僼傿儔儊儞僩偺惢憿岺掱 |
僫僀儘儞僗僥乕僾儖偺惢憿岺掱 |
|||||
|
|
||||||
傾僋儕儖
傾僋儕儖偺億儕儅乕偼擬偱梈偗傑偣傫丅梈偗偰傕暘夝偟偰偟傑偆偺偱丄梟梈朼巺偑偱偒偢丄梟嵻偵億儕儅乕傪梟偐偟偰朼巺偟傑偡丅偙偺梟嵻偑奺幮偦傟偧傟堘偭偰摿挜偑偁傝丄傑偨慇堐偺惈擻傪椙偔偟丄愼怓惈傪岦忋偡傞偨傔偵傾僋儕儖億儕儅乕偵彮検偺壔妛惉暘乮嫟廳崌尨椏乯傪堦弿偵偔偭偮偗傑偡偑丄偙偺壔妛惉暘傕奺幮偦傟偧傟堘偄傑偡丅
摿挜偲偟偰偼丄晽崌偑梤栄偵傛偔帡偰偄傑偡丅愼怓偑梕堈偱丄敪怓偑旤偟偔乮僇僠僆儞愼椏偱丄懠偺慇堐偼僇僠僆儞愼椏偱愼傑傜側偄乯丄抁慇堐偑庡懱偱朼愌偟傗偡偄慇堐偱偡丅検嶻偟傗偡偔丄僐僗僩傕埨偔偁偑傝傑偡丅擬僙僢僩惈偼偁傝傑偣傫丅80亷慜屻偱廮傜偐偔側傝傑偡丅僺儕儞僌偑婲偙傝傗偡偄偱偡偑丄峈僺儖僞僀僾偺傾僋儕儖傕奐敪偝傟偰偄傑偡丅
丂
 |
||||||||||
|
愇桘 |
僾儘僺儗儞 |
傾儞儌僯傾 |
傾僋儕儖 |
|||||||
|
傾僋儕儖 |
||||||||||
|
嫟廳崌 |
嫟廳崌 |
|
||||||||
|
梟嵻 |
梟夝 |
|||||||||
|
|
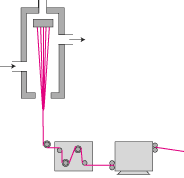 |
丂 | 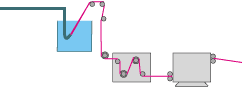 |
|
姡幃朼巺 |
幖幃朼巺 |
|
|
傾僋儕儖偺朼巺岺掱 |
||
傾僋儕儖偺80亷偱廮傜偐偔側傞惈幙傪棙梡偟偰僴僀僶儖僉乕巺傪偮偔傞偙偲偑偱偒傑偡丅
100乣120亷偱僙僢僩偟偨傾僋儕儖慇堐傪80乣90亷偱20乣30%堷偒怢偽偟偰偍偄偰丄堷偒怢偽偟偰偄側偄慇堐傪儈僢僋僗偟偰朼愌偟巺偵偟偰丄師偵100乣120亷偺擬傪壛偊傞偲丄堷偒怢偽偝傟偨傾僋儕儖慇堐偼僙僢僩偝傟偨宍忬傪巚偄弌偟偰尦偵栠傝傑偡丅1杮偺巺偺拞偱丄尦偵栠偭偰弅傓慇堐偼拞偵擖傝丄弅傑側偄慇堐偑奜偵晜偒弌偰傆偔傜傒偺偁傞巺偑偱偒傑偡丅偙傟偑僴僀僶儖僉乕巺偱偡丅偙傟偼僯僢僩偵揔偟偨椙偄晽崌偺巺偱偡丅
|
|
||||||
|
100乣120搙偱 |
80乣90搙偱 |
堷偒怢偽偟偨忬懺偱 |
100乣120搙偺擬傪壛偊傞偲丄 |
|||
| 丂 |
億儕僂儗僞儞
億儕僂儗僞儞宯抏惈慇堐乮僗僷儞僨僢僋僗乯偼1937擭偵僪僀僣偱敪柧偝傟偨僂儗僞儞宯乮旕抏惈乯慇堐惢憿媄弍偑婎偵側偭偰偄傑偡丅
愇桘壔妛偐傜嶌傜傟傞悢庬椶偺壔妛昳傪斀墳偝偣偰丄挿偄慄忋偱偟偐傕拞偵孅嬋偟傗偡偄晹暘傪帩偮億儕儅乕偐傜偱偒偰偄傑偡丅僑儉昍傛傝傕廮傜偐偔丄傛偔怢傃傑偡乮5乣7攞乯丅怢傃偰傕傑偨傛偔弅傒丄弅傓椡傕揔摉偱偡丅僑儉傛傝擬偵嫮偔丄僑儉偺傛偆偵偼傗偔榁壔偟傑偣傫偑丄5擭偔傜偄偱楎壔偟傑偡丅傑偨丄墫慺偺嶌梡偱墿曄偟偨傝丄楎壔傪懀恑偟偨傝偟傑偡丅愼怓偱偒傞揰傗丄僑儉偱偼晄壜擻側旕忢偵嵶偄巺偑帺桼偵嶌傟傞偺偼旕忢偵曋棙偱偡丅
巊梡偡傞偲偒偼丄昁偢丄懠偺巺偲堦弿偵巊梡偟傑偡丅
傑偨億儕僂儗僞儞傪棁偱丄懠偺巺偲堦弿偵曇傒崬傓偙偲傪儀傾儎亅儞巊偄偲偄偄傑偡丅儀傾揤偲偼丄儀傾儎亅儞巊偄偱娵曇婡偵偐偗偨揤幈曇暔偱偡丅